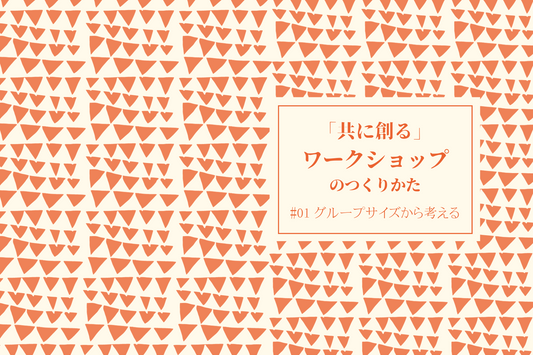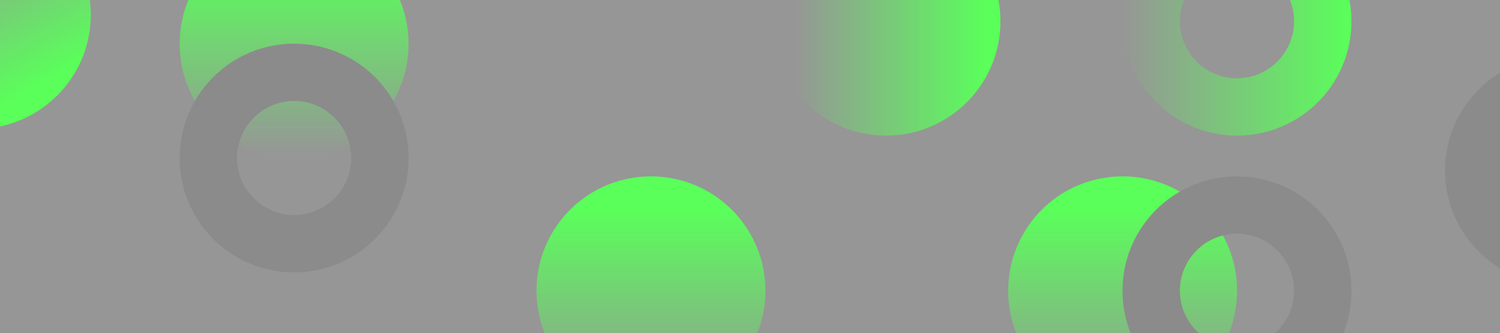こんにちは!FRACTA Research & Implementation(RI)局の月森です。
ブランディングの過程で実施されるワークショップにおいて、参加者全員が結果を自分ごと化できるための工夫を「場」という観点から考察する本シリーズ。前回はグループサイズごとの特徴を考えましたが、今回は「レイアウト」に着目して考えてみたいと思います。
▶「共に創る」ワークショップのつくりかた #01:グループサイズから考える
カフェで会話がはずむのはなぜか?
本題に入る前に、ワークショップに限らず、みなさんの日常生活を少し思い出してみてください。仕事の合間に少し息抜きをしたい時、また休日に気の置けない友人と会話する時、カフェを利用することがあると思います。そして多くのカフェでは、円卓を数人で囲める座席になっていたり、四角いテーブルで向かい合わせに座るようになっていることが多いのではないでしょうか。筆者は、話をする相手の様子がよく見える時、ラフでオープンに語れるような気がします。
実際、相互作用を促進させ対人関係を発展させるためには、駅のベンチのように壁に沿って椅子を横に並べる配置や、ランダムに椅子を配置させるよりも、カフェのテーブルのような配置がもっとも効果的だと述べている論文もありました。
このように、人が集まった場で相互作用を生むためには、「場のレイアウト」も工夫してみるのが良さそうです。
レイアウトごとの特徴
それでは、ワークショップの場でよく用いられるレイアウトごとの特徴をまとめていきます。
①教室(スクール)型

「話す側」「聞く側」という構図となり、参加者が受け身になりがちなため、話し合う場面にはあまり向いていません。ただし、ワークショップの中でインプットに特化する時間を設ける場合は取り入れても良いかもしれません。机を少し斜めに傾けて並べることで参加者同士お互いの顔が見えるようになるので、少し和やかな雰囲気にすることができます。
②コの字型

参加者同士が顔を合わせることができ、真ん中のスペースにファシリテーターが入り進行する構図を取りやすいです。ただし、15人くらいまでが理想で、それ以上の人数になると互いの距離が遠くなり、コミュニケーションが生まれづらくなります。
③島(アイランド) 型

机を何台か寄せて島を作るレイアウトです。参加者同士の距離が近くなり、顔がよく見えるのでグループワークに向いています。島のサイズを大きくしすぎないことがポイントです。丸テーブルを使うことも効果的で、全員が自然で対等な立場で肩肘を張らずに話すことができます。
④扇 (劇場 シアター) 型

机を使わず、椅子を扇形に並べるレイアウトです。机がない分お互いの距離が近くなり、参加者同士でちょっとした会話をすることもできるので一体感が増します。大人数の収容も可能です。ファシリテーターが全員をよく見ることができるので、オープニングやクロージングに適しています。
⑤バズ型

机を使わない島型のようなレイアウトです。よりくだけた雰囲気になります。人の移動も容易で、参加者の交流を深めながらコミュニケーションすることに適しています。
⑥サークル(キャンプファイヤー)型

円形に椅子を並べるレイアウトです。参加者がお互いに目線を合わせやすく、話し合いに集中できます。また、全員で話し合っているという一体感も生まれやすいです。皆で円になって座っていると何だか安心感を覚えるのではないかと思います。一方、この配置は緊張してしまう人もいるので、注意が必要です。
番外編として、このレイアウトをオンラインの話し合いでも応用することができることもお伝えします。
miroなどのオンラインホワイトボードを用いて参加者が自分の意見を記した付箋などを円状に貼り付けていく方法です。この時、色を変えたり記名したりすると、分かりやすく、それぞれが参加しているリアル感も出すことができます。筆者の経験では、それぞれの意見が円になって可視化されるので、安心感を持ちながら話し合うことができるように感じました。
⑦床・地面に座る
床に直接座る形です。よりカジュアルでアットホームな雰囲気になりますが、抵抗感のある人もいるので、参加者の状況やワークショップのテーマ・内容に応じることが必要です。
「非日常性」がポイント
今回はワークショップにおける「座席レイアウト」という観点から、効果的な場づくりを考えてきました。
前半にも述べましたが、レイアウトを工夫することで、人々の相互作用を促すことができると言われています。参加者の特性やどんな場にしたいか(インプットに集中してほしい、多くの参加者とお互いに交流してほしい、気軽に自分の意見を出してほしい、一体感を高める時間にしたい等…)に応じて、適宜設定してみてください。また、会場選びの際は目的のレイアウトが実現可能か、という観点でも検討することをお勧めします。
筆者は、ワークショップにおいては「非日常性」をつくりだすことも重要なのではないかと思います。普段の業務とは違う環境で、違うメンバーと取り組むことで創造性がかき立てられ、新しい意見や気づきが得られるのではないでしょうか。リフレッシュすると良いアイデアが浮かんでくることと似ているかもしれませんね。実際に、新しい環境に身を置くと脳にポジティブな刺激がもたらされるという研究もあるそうです。
第1回の記事で述べたグループサイズに加えてレイアウトも工夫してみることで、非日常性を演出し、ワークショップをより効果的なものにできるでしょう。これらはワークショップのみならず、会議やその他コミュニケーションを生む場でも応用できると思います。ぜひご活用ください。
次回は連載の最終回として、「周囲の環境」としてどんな工夫ができるのか、そしてこれらの工夫を何のためにするのか=ワークショップにおけるカギは何なのかを考えていきたいと思います。
▶「共に創る」ワークショップのつくりかた #03:その他の環境を考える
[参考]
- 「ワークショップ・デザイン: 知をつむぐ対話の場づくり[新版]」(堀 公俊、加藤 彰:日本経済新聞出版 2023年)
- 「着席行動及び座席配置に関する研究の動向」 〔山口 創:心理学評論 1996: 39 (3) : 361-383〕
- 研究で判明「移動中や旅先で仕事がはかどる」理由 「環境を変えるだけ」で作業効率が劇的に上がる(東洋経済ONLINE 2022年9月16日)